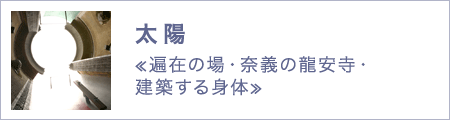太陽の部屋
≪遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体≫

前方から光が襲って来る。この部屋は真南を向いている。そしてシルエットになった一対の渦巻、中国伝来の「陰陽」の模様(太極図)。よく見て、空間関係を調整して了解しようとすると、左右にやや小さいが京都の龍安寺そっくりの石庭が、実は真南を向いた円筒の部屋の中心軸を対称にして対に置かれている。
あるいは円筒の内側に沿って180度回転した位置関係と言うべきか。さっきの渦巻きのuzuシルエットは龍安寺の油土塀の壁と屋根であった。寺を訪れても、普通はこの右側の庭のように、石庭を背後上方からは見えないという。ここでは岩の背後も見える。不思議なのは、すぐそこにある石庭の縁まで歩いて行けそうなのに、行けない。円筒の曲面の傾斜が急で登り切れないのだ。1/8という円筒の縦方向の傾斜もあって、歩ける場所はかなり限られている。どんな姿勢をとっても、何処に身体を置いても落ち着かないのだ。重力のおかげで身体の主軸方向は保たれるにしても、対応する水平軸は見当たらないし、不安定を強制されている感じがする。視覚的イメージとその他の身体感覚の告げるイメージが〈ずれて〉いるからだろう。普通、美術館とか展覧会といえば、視覚優先でことが済まされる。しかしここでは勝手が違う。意識が身体から、あるいは身体が意識から前のめりに〈ずれて〉しまっている感じ。その不安の隙間やギャップは何なのだろう。

赤と灰色に塗り分けられた床には曲面のベンチ、斜めに置かれたシーソー、鉄棒。これらには、座ったり、乗ったり、ぷらさがったりすることができる。緑と灰色の天井にはそれらと対応する、しかし大きさだけ1.5倍の同じものたち。
だが床とか天井とか言っても、この傾いた巨大な円筒型の部屋のなかでは何か意味をもつのだろうか。重力さえなければ天井のベンチやシーソーや鉄棒に座ったり、乗ったり、ぶらさがったりできるのだがと思いながら、 bench この部屋で一番落ち着くであろうベンチの真ん中、その曲面の〈底〉に座り込み、といっても後方に傾いているので、ここもそんなに落ち着きはしないのだが、周りを眺めている。するといつしか、身体に捕らわれている私の意識は、なにも〈ここ〉にいなくてもよいのではないかと思えてくる。
私自身には残念ながら、幻視の能カもないし、離魂体験もないのだが、上下、左右、前後が入れ替わっても、そして〈ここ〉と〈そこ〉が入れ替わっても、何の不都合もないのだろうなと思えたりする。それからこんなふうに考えている〈自分〉が、同じ様に考える〈他者〉と入れ替わってもいいのかなと思う。大体が、皆が同じ様に考えたり感じたリするならば、一人生まれて、成長し、老いて死んで行くとされている個の〈意識〉とか〈生〉とは何なのだろう。父、母、夫/妻、子、同胞…、〈共同体〉とは、蟻のような社会でないにしても、ひとつの生命体、意識なのだろうか。それは生物学で言うような〈種〉などだろうか? 時間にも前と後があって、過去、現在、末来と、〈矢〉のように一方向に進んで逆戻りができないのだろうか。
この空間は、ここに来た人達の身体に、まず日常とは異なった身体の経験を強制し、不思議な雰囲気を生まれさせ、そして考えさせる。それはどうも空間についてだけではなさそうだ。身体が告げている、もっと根源的な能力の目覚めのようなもの。〈非人称〉の視点の入手。〈私〉と〈他者〉が〈出来事〉のなかで新生する。

しかしなぜ龍安寺なのだろう? アラカワ/ギンズは、人工によって〈懐かしさ〉を「建築する」ことを目指している。この部屋に「心」と名付けているのもそれによる。最初の計画案では、垂直の円筒型の建築物の中に倒立した法隆寺があって、「胎内潜り」のように、その法隆寺を潜って行くと何時しか建物の外部に出ているというものであったと思う。それがこの傾斜する龍安寺の石庭へと計画変更されて、実現した。「胎内潜り」の要素は外部が見えない部屋や階段にそのまま残されているが、寺院の建物は枯山水の庭に変わった。 sekitei どちらにしても皆が知っている有名な〈日本的なもの〉であることに変わりはない。このアラカワ/ギンズの言う「日本の懐かしさ」は、だが下手をすれば、現代の日本人にはキッチュに見えたり、気恥ずかしく思われているものとなるかもしれない。それでもアラカワ/ギンズはあえてそれを題材に選んだ。彼らにとっては、日本回帰やキッチュとかいった文明人の屈折などは突き抜けたストレートな提示が問題なのだ。ここでは揚げ足取りや気難しい保身はひとまず脇に置いていこう。誰でも知っている〈あれ〉。禅寺の庭。枯山水。それらは「見慣れているもの程よい」と言う。有名なお寺の庭の岩や草や苔といったもの。奈義の美術館のこの部屋は、彼らが長年かけて追究している実験のうち、やっと実現した〈半恒久的な〉実験施設なのだ。そういえば幾つもの計画が実現されないままだ。それでも彼らは探究を止めない。絵画、建築模型、展覧会、コンピューター・グラフィックス、対談、出版…。

入口の小部屋、階段そして円筒の部屋と、仕組まれているのは、知覚・身体感覚のエクササイズ(演習・実行)である。自己意識と身体感覚のバランスが崩れ、〈軸〉がずれ、意識が前のめりになって〈二重化〉がおこり、「何か」が生まれ出る。それは新生児の知覚にあって、私たちが大人になるにつれて忘れてきたもの。それは「不安」や「信仰」「心」と呼ばれるもの。私たちの〈根〉であり、「懐かしさ」とでも呼ぶのか、ある〈雰囲気〉である。人工的に「インスタント・ノスタルジー」を作り上げることと彼らは言う。現代思想に見られる言葉での停滞を打破すべく、「与えられたもの」を使って、人工的に構築すること。言葉ではなく、構築物と身体の側からの可能性を実験してみること。ここで彼らは何を起こそうとしているのか、そして実際何が起こるのか、そして何を持ち帰れるのか、こうしたことが訪れた人の課題である。
<『奈義町現代美術館』常設カタログ「3つの会話 高橋幸次(東京国立近代美術館研究員)」より抜粋>
- 展示室「太陽」
- 遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体
今から一億年のイベントに向かってここに進み入りましょう。
「始まり」「過去」「未来」「私が」「私に」そして「あなた」はここではすべて意味がありません。それらは一億年という過程にとっては余分なものです。
永遠とは化石じみた愚かな夢あるいは解釈です。不死とは無論まったく別物です。どのようにして死から逃れるかを知るために、《遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体》へと入りましょう。
不均衡な均衡状態の中で肉体は磁気を帯びたように動き、人は肉体を離れてアイデンティティを得ます。シンメトリーがアイデンティティに取って替わるでしょう。シリンダーの中ではそれは可能であり、事実、そうなのです。
シリンダー内には、かつて肉体が動作を制御していたようなものは何もありません。
あなたはシリンダーの中に入っていく、しかし、もしあなたが動作をつかさどる肉体として入っていったのなら、途端に無に帰するでしょう。一度均衡状態が崩れると、おそらく同じようにシリンダーによってしか、それを回復することはできないのです。
シリンダー内には一度にたった一人 -もし二人が本当に一つに成り得るならたぶん二人- しか入れません。シリンダーは人の領域を拡張するのです。
シリンダー内では肉体が、かつてないほど完璧に環境の中の存在として人間を認知させます。肉体はシリンダーあるいはシリンダーのシンメトリーに対して自己を失います。シリンダー内のすべての物体、あらゆる面、さまざまなズレが、かわるがわる、肉体によって自己を導きます。
人間がつくりだした世界と完全に適応する自分を見つけだすとは奇妙なことですが、さらに奇妙なのは、来館者がこのシリンダーの中に入ると肉体があやつり人形のようになってしまうことです。例えば、シリンダーの壁に固定された岩は、訪問者の内部に表われた目に見えぬ岩のイメージよりもさらに身近に感じられるのです。
前室を通って生理的にも精神的にもほどよく疲れた後、訪問者は形も時間も自分自身へとうねり返ってくるカプセルの中へ、階段を登って入り込みます。そこには大きな今のほか何もありません。
大きな今において肉体をつかさどるのは、シリンダー内のあらゆるものと、初めてシリンダーへと導いてきた肉体を構成するすべての要素とのアマルガムであり、人はすべてを新鮮に感じる永久のバージンとなるのです。永久のバージンにとって先立つ龍安寺は存在しません。このシリンダーの庭がオリジナルなのです。シリンダー内のものはすべて、ごくありふれた、この上もなく身近なものなのに、シリンダー内で動くと誰もこのことに気づきません。ひとたびシリンダー内に入ってしまうと、誰もが、何もかも新鮮でオリジナルな永久のバージンになるのです。
シリンダー内には新たなものなど何もないのに、どうして大きな今や永久のバージンが浮かび上がってくるのでしよう? 位置がすべてなのです。あらゆる知的なイメージ操作と建築的な場が疑問の余地なく正確に配置されることで、「心」はついに心と出会い、包み込んで共振し、どのようにして死から逃れるかを教えます。私たちは長い間、シンメトリ一が、そしてシンメトリ一だけがこの状態をもたらすに違いないという強烈な直感的洞察を養いつつそれと共生してきましたが、今、大変うれしいことに、本当にそうだということに私たちは気づくのです。
距離感を喪失させるために補色が天井と床に用いられていますが、「大きな今」は補色的な色使いに、それぞれが自己を必ず発見するというより大きな役割を与えるのです。
荒川 修作 + マドリン・ギンズ
(訳:GA JAPAN編集部) 愛子